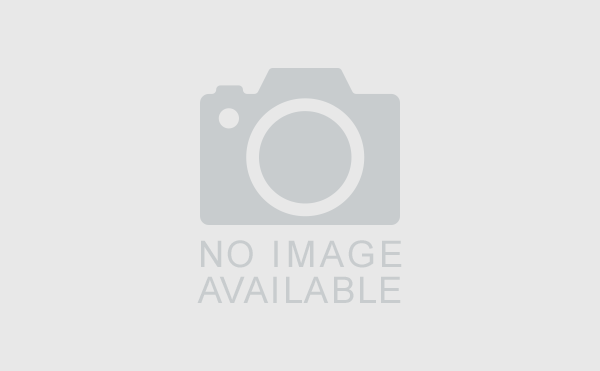褒める基準と叱る基準
でも、やっぱり人を「叱る」のは「褒める」よりエネルギーが要りますね。 みなさんは、「褒める」と「叱る」の基準をどこに設定されていますか? その基準について考えてみたいと思います。
褒める基準
なんの為に褒めているのか?もちろん子供たちの能力を伸ばそうと思って褒めています。 しかし、やみくもに「すごい!」「上手!」と褒めていても子供達は何がよかったのか分かず、次に繋がらず褒めるではなく「おだてる」になってしまいます。 子供を褒める一番の目的は「自己肯定感を高める」事だと思っています。
自己肯定感とは簡単に言うと「自分を認める」「自分に自信を持つ」と言う事です。
自己肯定感が強くなると「失敗をしても打たれ強く、チャレンジできる」子供に育ってくれます。→打たれ強い選手になってほしい自己肯定感を高める
子供を褒める一番の目的は「自己肯定感を高める」事だと思っています。
自己肯定感とは簡単に言うと「自分を認める」「自分に自信を持つ」と言う事です。
自己肯定感が強くなると「失敗をしても打たれ強く、チャレンジできる」子供に育ってくれます。→打たれ強い選手になってほしい自己肯定感を高める
能力を褒めても効果がない
アメリカで褒める事に対するこんな研究があります。 子供たちを400人を対象に知能テストを行った。子供たちにはテストの採点結果は教えずに、全員に80%正解できたと伝えたそうです。 その後、400人を2つのグループ分けました グループ1には「問題が解けたのは、君達が本当に頭がいいからだ」と話し、グループ2には何も言わない。 そして、次の課題を2つ提示して選んでもらいます。 ①非常に難しくて解けないかもしれないが、やりがいがあって、学びの多い問題 ②非常に簡単でスラスラ解けるが、学びは少ない問題 【結果】
頭がよいと言われたグループは65%が簡単を選んだ、何も言わなかった方は45%が簡単を選んだ。
つまり、頭がよいと褒められた方は「次に失敗をすると恥ずかしい」とチャレンジしなくなり、頑張らなくても良くできると思いがちになってしまうのです。
【結果】
頭がよいと言われたグループは65%が簡単を選んだ、何も言わなかった方は45%が簡単を選んだ。
つまり、頭がよいと褒められた方は「次に失敗をすると恥ずかしい」とチャレンジしなくなり、頑張らなくても良くできると思いがちになってしまうのです。
努力を褒める
この研究結果を聞くと「褒めるのはよくない事」なのかと思ってしまいますが、そうではなく、「結果を褒めるのはよくない」と捉えて欲しいです。 「君は天才だ」「君の才能は素晴らしい」これでは子供は伸びないと言う事です。 「君がこの結果を出せたのは、今日まで一生懸命やってきたからだ」 「君の才能は上手くなるまで、努力を続けられる事だ」 「結果」ではなく、そこへ辿り着くまでの「努力」を褒める事が重要です。 努力を褒める事で、次に大きな壁にぶつかった時にまた頑張って乗り越えようと言う気持ちを育てる事が出来ると思っています。叱る基準
私は普段から褒める事は重要と書き続けてきますが、「叱らない」という訳ではありません。 「褒めて育てる」「厳しく育てる」これはどちらか一方が正しいという答えはありません。 子供たちの努力を褒め、判断(考え)のあるプレーを褒めます。逆にいい加減な態度は注意して、判断のないプレーはそれが正しか子供たちに問いかけます。
そして、
「子供自信や他人が傷つく(怪我、精神的にも)行為」は躊躇なく叱ります
「社会のルールから大きくはずれるような時」も躊躇なく叱ります
今までの経験で例を挙げると
「あいつはサッカーが下手だから試合に一緒に出たくない」
「お前バカか、死ね」
こんな声が聞こえた時は、躊躇なく叱りました。
駐車場でボールを蹴っている。高い所に登っている。小さな子供のいる方へボールを蹴っている。
大きく2つの基準から外れた時は「叱る」という行為で子供たちに理解をしてもらうようにしています。
子供たちの努力を褒め、判断(考え)のあるプレーを褒めます。逆にいい加減な態度は注意して、判断のないプレーはそれが正しか子供たちに問いかけます。
そして、
「子供自信や他人が傷つく(怪我、精神的にも)行為」は躊躇なく叱ります
「社会のルールから大きくはずれるような時」も躊躇なく叱ります
今までの経験で例を挙げると
「あいつはサッカーが下手だから試合に一緒に出たくない」
「お前バカか、死ね」
こんな声が聞こえた時は、躊躇なく叱りました。
駐車場でボールを蹴っている。高い所に登っている。小さな子供のいる方へボールを蹴っている。
大きく2つの基準から外れた時は「叱る」という行為で子供たちに理解をしてもらうようにしています。